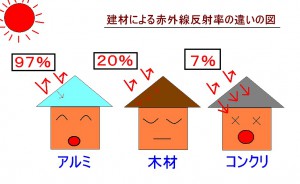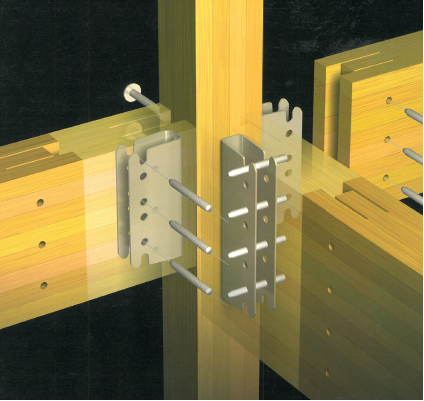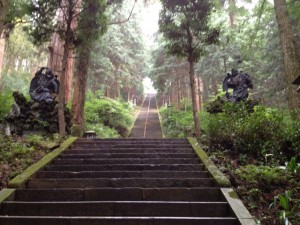前回投稿致しましたアパート工事
「SR大岡山102号室」
全て終了しました!
とても綺麗なお部屋に仕上げることが出来ました(#^.^#)
新築同然の洋室。白く清潔感のある空間になりました!
クローゼットも二つあり、収納力抜群!!(^_^)/
ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。駅近ですよ(^_^)/
☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-
ちなみに佐々木は先週末、鎌倉散策をして参りました。
鎌倉駅→佐助稲荷神社→ハイキングコース(山道)→鎌倉大仏→長谷寺→由比ヶ浜
→江ノ電(鎌倉駅へ)→鶴岡八幡宮→鎌倉駅→脚パンパン
10㎞以上歩きました(^_^)
やはり鎌倉は観光名所が多く、お寺好きとしては何度行っても飽きませんね!